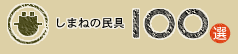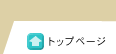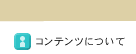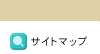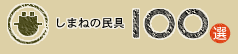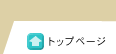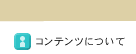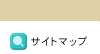|
 |
 |
 |
|
 |
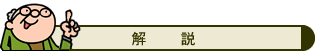 |
 |
羽釜(はがま)で炊けたご飯を移しておく容器です。杉板を組み合せて作った桶で、常に温かいご飯が食べられるように、竹か真鍮(しんちゅう)の輪で締めて、すき間がないように作ってありました。柿渋を毎年塗って常に清潔に保っていました。形は円形または楕円形で、楕円形の場合には取手がついています。大きさは一升飯用、2升飯用が一般的で、まれに一斗(いっと)飯用がありましたが、これは田植えなど多くの人が仕事をするときに使われました。 |
 |
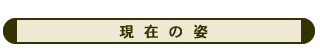 |
|
昭和40年ごろになると電気炊飯器が使われだし、炊けたご飯をジャーなど電気で保温します。さらに炊飯・保温の機能を備えた炊飯ジャーに替わっていきます。 |
|
|
 |
|
|
|
|