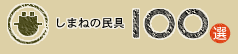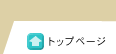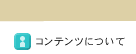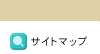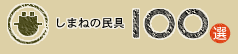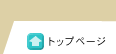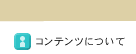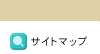|
 |
 |
 |
|
 |
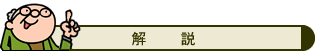 |
 |
糸車の車は竹製で、台は木でできています。昔の農家では木綿を栽培し、それを綿にして糸車で糸にしていました。糸車は、主に農家の婦人が使っていましたが、その操作にはかなりの熟練が必要でした。綿打屋(わたうちや)で打った綿を、糸車で一本の単糸にひき、それを撚り合せて、木綿針のミズを通る程の細糸に仕上げる人もいました。また、糸車は、木綿糸だけでなく、紙布(しふ)用の紙糸や、繭からひいた単糸を撚り合せて絹糸にもしました。 |
 |
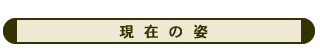 |
|
使用開始年代は不明ですが、江戸時代から明治時代にかけて使われていました。昭和20年前後、日本国中物資が不足し、食糧品ばかりか衣料品も配給制となり、日常の衣服の補修やボタン着けに使う糸も手に入らない時期がありました。その時、糸車を上手に使って、木綿糸をつくっている老婦人もありました。 |
|
|
 |
|
|
|
|